
中学校に入ると様々な部活がありますが、その中でも文化系の部活に吹奏楽部がある学校は多いはずです。
吹奏楽は、楽器を使った部活ですので非常に人気があります。
とくに音楽が好きになるのは男性よりも女性の方が多く女子生徒には人気の部活です。
女子生徒のうち3割ぐらいが吹奏楽部に入っている学校などもあり、部員全体の9割が女子生徒の可能性もあります。
このように考えると、よほど小さな学校でない限り吹奏楽部を抜かして部活動を考えることができないでしょう。
… もっと読む
ピアノ/吹奏楽/クラシック/声楽/声優/ギターのノウハウや情報が満載
by m

中学校に入ると様々な部活がありますが、その中でも文化系の部活に吹奏楽部がある学校は多いはずです。
吹奏楽は、楽器を使った部活ですので非常に人気があります。
とくに音楽が好きになるのは男性よりも女性の方が多く女子生徒には人気の部活です。
女子生徒のうち3割ぐらいが吹奏楽部に入っている学校などもあり、部員全体の9割が女子生徒の可能性もあります。
このように考えると、よほど小さな学校でない限り吹奏楽部を抜かして部活動を考えることができないでしょう。
… もっと読む
by m
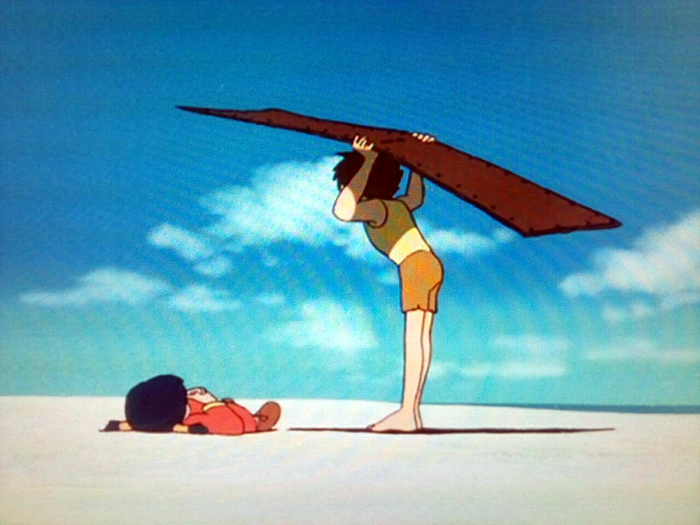
吹奏楽とアニメは関わり合いが深いものになり、吹奏楽を題材としてたものも多いですし、吹奏楽でアニメが使っている曲を演奏することもあります。
お互いに相性が良く、相乗効果によりアニメで吹奏楽が題材にされた物は人気が高いですし、コンサートでアニメの曲を演奏した場合にも大きな反響をする事ができます。
吹奏楽もアニメも学生が主役になるので、共通点が多いのも特徴です。
… もっと読む
by m

美しい音を奏でている吹奏楽は、誰もが心を奪われてしまうほどの魅力を持っています。
一人だけで演奏するのではなく大勢のメンバーと一糸乱れぬ音をだすためには、毎日の厳しいトレーニングを続けているからこそできることです。
美しい音をだすためには、ロングトーンをしっかりとできるようにすることが大切になります。
ロングトーンとは同じ音を長くだし続けることで、できるだけ長くできるようにすることが大切です。
長く音をだすだけなので、それくらいなら簡単にできると考えてしまう人が少なくありません。
… もっと読む
by m

吹奏楽は吹いて演奏する音楽と書きますが、楽器の選択または演奏の編成によって定義されるものです。
管弦楽、いわゆるオーケストラの場合は木管楽器・金管楽器・打楽器、そしてバイオリンやチェロなどの弦楽器があります。
吹奏楽では、これらのバイオリンやチェロのような弦楽器は使用されておらず、特有の楽器にはサキソホンとユーフォニウムを持っています。
これは吹奏楽の発祥が行進曲の演奏にあるからです。
… もっと読む
by m

トロンボーンは音程が正確に取れる割には、構造がシンプルであることから吹奏楽では欠かせない楽器と認識されています。
その特徴は人間の発声との調和を取るのに向いており、ハーモニーの美しさで魅了される点にあると言えます。
さまざまな楽器の中にあって、人間の声に最も似ている声との印象を持つ人も少なくありません。
ただスライド操作を伴う為、早いパッセージは苦手と言う側面を持っているので独奏するには向いておらず、あえて専門に取り組む独奏家も少数に止まっています。
現実は一部の意欲的な演奏家が専心してレパートリーの拡大と魅力の発進に勤めているのに止まっているのが現状で、ソロ楽器の認知度は低いままに止まっているのです。
… もっと読む
by m

日本では昔から吹奏楽の人気が高いです。
吹奏楽とは管楽器を主体とした音楽ですが、コントラバスや打楽器なども編成に含まれています。
現在では電子楽器が加わることもあります。
学生やアマチュア吹奏楽団を対象にしたコンクールも多く、特に全日本吹奏楽コンクールは有名です。
楽器の中で人気が高いのがトランペットですが、トランペットは長い歴史を持っています。
… もっと読む
by m

ディズニーはアニメが楽しいのはよく知られるところですが、吹奏楽があるとさらに楽しめるという事もあります。
ディズニーはアニメにもこだわっていますが、音楽にもこだわっているといってもいいでしょう。
その為アニメが人気になると同時に音楽も人気になるという事が良く起きています。
恐らくはディズニーは目で見て耳で聞いて楽しむという事を常に考えているからそうなるのでしょう。
最近ではさらには触覚なども考えているのかもしれません。
将来的には見て聞いて触って楽しめるという夢のアニメが出来るようになるのかもしれない。
そうなると臭覚なども使ってくることがあるのかもしれません。
… もっと読む
by m

日本には多くの吹奏楽部があり、中にはコンクールで何度も優勝するような名門校もあります。
夏に行われるコンクールは、名物イベントとして有名です。
コンクールに参加する学校は早いうちからスケジュールを決めて、上位に入れるように熱心に練習を続けています。
… もっと読む
by m

高校生で部活を始める場合は、吹奏楽部がお勧めです。
吹奏楽部は本格的に力を入れている学校が多く、高校生で始めると一生の思い出作りをする事が可能です。
実力によっては全国大会に出場する事もできるので、自分の力を試す事が可能です。
また音楽に触れる機会も多くなるので、自然とクラシックなどにも詳しくなります。
有名なクラシックを自分で演奏できるようになるともっと吹奏楽が楽しくなる事に間違いありません。
… もっと読む
by m

吹奏楽を行うならブレストレーニングは必ず行いましょう。
吹奏楽はその名前の通り、息をコントロールする必要がある楽器を利用するので、息のコントロールが出来ないと上手く演奏する事が出来ません。
そこで、ブレストレーニングを行うことで、腹式呼吸をマスターする事ができる為、きちんとした演奏を行う事ができます。
ブレストレーニングは部活中だけではなく、自宅に帰ってから一人でもトレーニングする事ができるので、毎日行うほど、高い効果を得る事が可能です。
その為にもブレストレーニングのトレーニング方法をきちんと把握する事が大切です。
闇雲に行っても上手くいきませんので、きちんとしたトレーニング方法をマスターするようにして下さい。
… もっと読む